2025年6月、Googleのコアアップデートが実施され、多くのブロガーやサイト運営者の間で「MUVERA」という新しい言葉が囁かれるようになりました。これは一体何なのか? 新しいアルゴリズムなのか、それともGoogleが掲げる新しい理念なのか。情報が錯綜する中、ぼく自身も大きな混乱の渦中にいました。しかし、断片的な情報を一つひとつ拾い集め、HCSやE-E-A-TといったGoogleの基本理念に立ち返り、難解な専門用語を一つずつ噛み砕いていくうちに、ぼんやりとしていた霧が晴れ、進むべき道がはっきりと見えてきたのです。この記事は、そんなぼくが経験した「紆余曲折の調査の旅」そのものです。MUVERAの正体から、その根幹をなす技術、そして私たち個人ブロガーがこの新しい時代で何をすべきかまで、これまでの対話で得た知見を余すところなく、そして徹底的なファクトチェックを経て、一つの物語として紡ぎます。
2025年、SEO界を揺るがした「地殻変動」

それは、まさに突然の「地殻変動」でした。2025年6月のコアアップデートを境に、これまで当たり前だった景色が一変したのです。一部のサイトはアクセスを大きく失い、また一部のサイトは、まるで長い冬眠から覚めたかのように、検索順位を大きく回復させました。この変動の中心にあると囁かれたのが「MUVERA」という存在です。この未知の言葉に、多くの人が期待と不安を抱きました。AIが生成した回答が検索結果の上位を占める「AI Overview」によるトラフィックの喪失も現実味を帯び、これまでのPV(ページビュー)に依存したブログ運営が、根本から見直しを迫られる時代の幕開けでもありました。このセクションでは、まずあの衝撃的なアップデートが、私たちに何をもたらしたのかを振り返ります。
今回の変動は、単なる順位の入れ替えではありません。Googleが検索エンジンとして、次のステージに進んだことを示す明確なサインです。キーワードを詰め込み、外部リンクを集めるといった従来のSEOテクニックが急速に力を失い、「コンテンツの本質的な価値」が、これまで以上に問われるようになりました。情報検索クエリが多いジャンルでは、AIがユーザーの質問に直接答えてしまうことで、サイトへの訪問者数が15%から35%も減少したという報告もあります。これは、ただ記事を書いて待っているだけでは、ブログが誰にも読まれなくなる未来を示唆しています。この厳しい現実を直視し、変化の正体を理解することから、新しい時代のSEO対策は始まります。
検索を再発明する2つの新技術:MUVERAとGFM
今回のアップデートの核心を理解するためには、「MUVERA」と「GFM」という2つの技術的なコンセプトを知る必要があります。これらはGoogleが公式に発表した名称ではありませんが、アップデートの仕組みを理解するために世界中の専門家が分析し、たどり着いた概念です。この2つは、まるで車の両輪のように連携し、Googleの検索品質を新たな次元へと引き上げています。このセクションでは、この新しい検索エンジンの頭脳とも言える2つの柱について、その仕組みと目的を、比喩も交えながら詳しく掘り下げていきます。これらを理解することが、今後のコンテンツ作成の羅針盤となるはずです。
MUVERA:「キーワード」から「意図」を読み解く検索へ
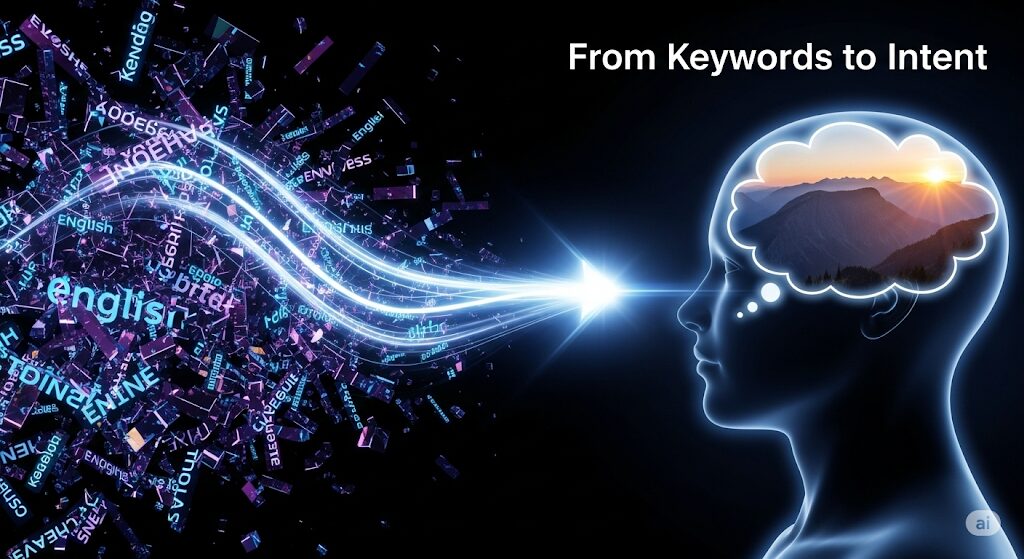
MUVERA(Multi-Vector Retrieval via Fixed Dimensional Encodings)とは、一言でいえば「ユーザーの検索意図を、より深く、より正確に理解するための技術」です。これまでの検索は、入力された「キーワード」にどれだけ近い言葉がページに含まれているかが重要でした。しかしMUVERAは、言葉の表面的な一致ではなく、その背後にある「文脈」や「ニュアンス」を読み解きます。例えば「最近疲れてて、癒やされる場所に行きたいな」というような曖昧な検索に対しても、ユーザーが本当に求めているのは「静かな温泉」「景色の良いカフェ」「自然豊かな公園」といった選択肢であることを理解し、最適な答えを提示できるようになるのです。これは、検索エンジンが「計算機」から「相談相手」へと進化していることを意味します。
ベクトル検索とエンベディング:言葉の「雰囲気」を理解する仕組み
このMUVERAの根幹をなすのが、「ベクトル検索」と「エンベディング」という技術です。難しく聞こえるかもしれませんが、これは言葉に「音楽のDNA」を付けてあげるようなものです。例えば「悲しい」と「切ない」は文字が違いますが、雰囲気が似ていますよね。この「似ている感じ」をコンピュータに教えるのがこの技術の役割です。言葉や文章を分析して、その意味や雰囲気を表すユニークな「DNA」、つまりコンピュータが処理しやすい数値の集まり(ベクトル)に変換します。これにより、コンピュータは文字としてではなく、このDNAが似ているかどうかで言葉の意味が近いかを判断できるようになります。音楽アプリが「この曲が好きなら、これも好きかも?」と似た雰囲気の曲をおすすめするのと同じ仕組みが、言葉の世界で実現されているのです。
マルチベクトル表現:複数の「タグ」でより精密な理解を
従来のベクトル検索では、一つの文章を一つのDNA(単一ベクトル)で表現していました。しかし、これでは複雑なニュアンスを捉えきれない場合があります。例えば「ロックだけど、歌詞は切なくて、静かなピアノソロもある曲」を、単に「ロック」という一つのタグで表現するようなものです。そこで登場するのが「マルチベクトル表現」です。これは、一つの文章に対して、大事な要素ごとに複数のDNA(タグ)を付けられるようにする考え方です。例えば、「安価で、女性向けの、アーチサポートがしっかりしたランニングシューズ」という複雑な検索に対して、「#安い」「#女性向け」「#アーチサポート」「#ランニングシューズ」といった各要素を個別のDNAとして捉えることができます。これにより、それぞれの意味の断片をより精密にマッチングさせ、ユーザーの細かい要望に応えることが可能になるのです。
GFM:ウェブ上の「信頼」をマッピングする頭脳
GFM(Graph Foundation Model)は、MUVERAが「何が書かれているか」を理解する技術だとすれば、「誰がそれを書いているか」という信頼性を判断するための、もう一つの重要な技術です。GFMは、ウェブ上の無数の情報(著者、サイト、企業、論文など)と、それらの関係性を「グラフ」という巨大な相関図のように繋ぎ合わせて理解します。例えば、ある無名の著者が書いた健康に関する記事と、有名な大学教授が書き、医学雑誌からも引用されている記事では、後者の方が圧倒的に信頼性が高いと判断します。GFMは、このようなウェブ上の評判や情報の繋がりをマッピングし、「この分野なら、この人の情報が最も信頼できる」ということを、システムとして判断するのです。
すべての土台となるGoogleの哲学:HCSとE-E-A-Tの再学習
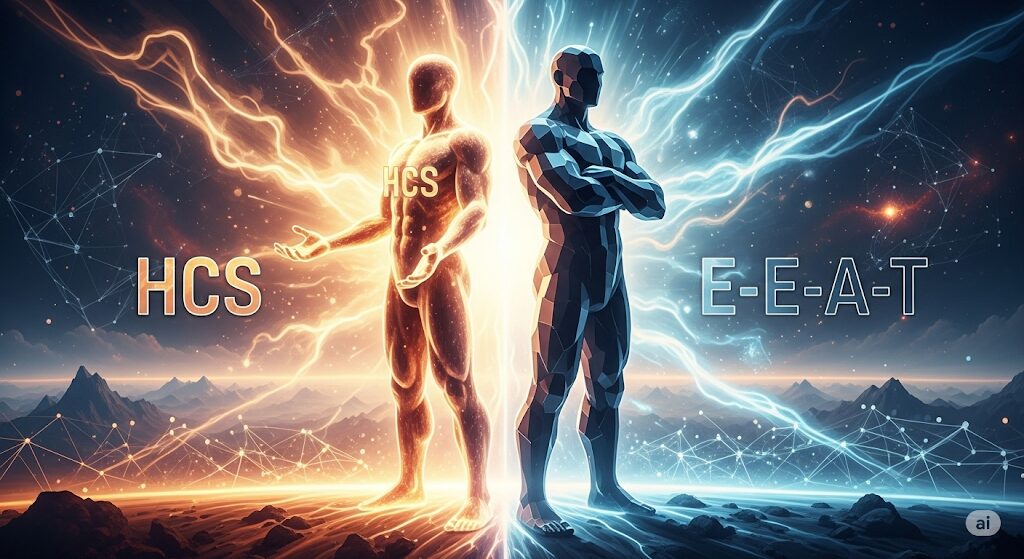
MUVERAやGFMといった新しい技術を理解した上で、次に私たちが立ち返るべきなのは、Googleが長年重視してきた「基本理念」です。なぜなら、これらの新技術は、この基本理念をより高いレベルで実現するために開発されたツールに他ならないからです。その理念の核心にあるのが、「HCS」と「E-E-A-T」です。これらは、単なるアルゴリズムではなく、Googleが考える「良いコンテンツとは何か?」という哲学そのものです。このセクションでは、多くの人が一度は聞いたことがあるであろうこれらの言葉を、ブログ初心者の視点に立って、改めてその本質から掘り下げていきます。ここを理解せずして、未来のSEOを語ることはできません。
HCS(ヘルプフルコンテンツシステム):それは「読者のためのコンテンツ」か?
HCS(Helpful Content System)とは、その名の通り「ユーザーにとって役に立つコンテンツ」を高く評価し、そうでないものの評価を下げるためのシステムです。ここで重要なのは、HCSが「検索エンジンのためだけに作られたコンテンツ」を非常に嫌うという点です。例えば、ただ検索上位を狙うためだけにキーワードを不自然に詰め込んだり、様々なサイトから情報を継ぎ接ぎしただけの中身のない記事は、HCSによって「役に立たない」と判断され、サイト全体の評価が下げられてしまいます。逆に、明確なターゲット読者を設定し、その読者の疑問や悩みを解決するために、心を込めて書かれた記事は高く評価されます。HCSは、Googleが「読者ファースト」を本気で徹底するための、強力な意思表明なのです。
E-E-A-T:Googleがあなたのブログを「信頼」するための4つの条件
E-E-A-Tは、GoogleがWebページの品質を評価するために用いる、非常に重要な指針です。これは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、そしてTrust(信頼性)の4つの頭文字を取ったものです。これらは、Googleがあなたのブログを「検索ユーザーに安心して紹介できる、本当に良いブログだろうか?」と判断するための、具体的なチェックポイントです。これら4つの要素は、ブログ運営において常に意識すべき、いわば「北極星」のような存在です。特に、お金や健康、安全といった人々の生活に大きな影響を与える「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼ばれるジャンルでは、このE-E-A-Tが極めて厳しく評価されます。
E – Experience (経験):あなたは本当にそれを「体験」しましたか?
一つ目の「E」は「経験」です。これは、あなたが記事に書いているテーマについて、実際に体験したことがあるか、という点です。例えば、最新のスマートフォンのレビュー記事を書くなら、実際にそのスマートフォンを購入し、使い込んでみないと、本当の使い心地は語れませんよね。ネット上のスペック情報や他の人のレビューをまとめただけでは、それは「経験」とは言えません。読者が求めているのは、あなた自身の言葉で語られる、リアルな体験談です。自分で撮影したオリジナルの写真や動画を掲載することは、この「経験」を読者やGoogleに伝える上で非常に効果的な方法です。
E – Expertise (専門性):あなたはその道の「マニア」ですか?
二つ目の「E」は「専門性」です。これは、あなたがそのテーマについて、どれだけ深い知識を持っているか、ということです。例えば、あなたが「ラーメンが大好きで、年間300杯は食べる」という人なら、あなたの書くラーメンの記事には、自然と専門性が宿ります。スープの出汁の種類、麺の加水率、チャーシューの作り方まで語れるかもしれません。このように、ブログのテーマを「あなたの『大好きで、得意なこと』」に絞ることで、誰にも真似できない専門性が生まれます。あれもこれもと手を出すのではなく、一つの分野を深く掘り下げることが、専門性を高めるための鍵となります。
A – Authoritativeness (権威性):あなたは周りから「頼れる存在」だと思われていますか?
「A」は「権威性」です。これは、あなたのブログやあなた自身が、その分野において「第一人者」や「頼れる情報源」として、周りから認められているか、ということです。これは自分一人で高めるのが難しい要素で、第三者からの評価によって確立されます。例えば、あなたのブログが、同じジャンルの有名なブロガーから「この記事はすごく参考になるよ!」と紹介されたり、SNSで多くの人から「この情報はすごい!」と共有されたりすると、権威性は高まっていきます。すぐには結果が出ないかもしれませんが、質の高い情報を発信し続けることで、徐々に「このテーマなら、あのブログだよね」という評判が生まれ、それが権威性につながるのです。
T – Trust (信頼性):あなたの言葉は「信頼」できますか?
そして、E-E-A-Tの中で最も重要とされるのが、最後の「T」、「信頼性」です。どんなに経験豊富で専門性が高くても、その情報が嘘だったり、発信者が誰だか分からなかったりすれば、誰もそのブログを信じてはくれません。信頼性を高めるためには、まず「正直であること」が大切です。良い面だけでなく、悪い面も隠さず伝えることで、読者との間に信頼関係が生まれます。また、「誰が」この記事を書いているのかを明確にするために、簡単なプロフィールページやSNSへのリンクを設置することも有効です。お問い合わせフォームを設置して、いつでも連絡が取れるようにしておくことも、読者に安心感を与え、信頼性向上に繋がります。
Googleの評価の仕組み:「編集者」と「校閲者」の二重チェック
ここまで、HCS(役に立つか)とE-E-A-T(信頼できるか)という、2つの大きな評価軸について見てきました。では、Googleはこれらをどのように使って、最終的なページの評価を下しているのでしょうか。この複雑な仕組みを理解するために、ぼくは「本の出版」という、とても分かりやすい例えにたどり着きました。Googleの評価システムは、まるで一冊の本が世に出るまでのプロセスのように、「編集者」と「校閲者」という二人のプロフェッショナルによる、厳しい二重チェック体制で成り立っているのです。このセクションでは、その具体的なチェックの流れを詳しく見ていきましょう。
第一の関門:「編集者(HCS)」による価値のチェック
あなたのブログ記事は、まず「編集者」の元に届きます。この編集者の役割は、GoogleのHCS(ヘルプフルコンテンツシステム)に相当します。編集者はただ一つ、「この記事は、読者が時間を割いてでも読みたいと思うくらい、面白くて役に立つか?」という視点だけで、あなたの記事を評価します。彼らは、読者の悩みが解決できるか、他にはない独自の視点があるか、そして何より書き手の情熱が伝わってくるかを重視します。どんなに情報が正確でも、退屈で読者の心を動かせない記事は、この編集者の段階で「出版する価値なし」と判断されてしまいます。読者にとっての「価値」や「魅力」を追求することが、この第一関門を突破するための鍵です。
第二の関門:「校閲者(E-E-A-T)」による信頼性のチェック
編集者の厳しいチェックを無事に通過した記事は、次に「校閲者(こうえつしゃ)」の元へ回されます。校閲者の役割は、E-E-A-Tの指針に沿って、その記事の「信頼性」を徹底的に検証することです。校閲者は、まるで虫眼鏡を覗き込むように、「この記事の情報は本当に正しいか?」「作者は信頼できる人物か?」「参考文献は明記されているか?」といった点を厳しくチェックします。特に、読者の安全や財産に関わる情報については、一切の妥協を許しません。この記事を書いたのは誰なのか、その人は語るに足る経験や専門性を持っているのか、そして第三者からの評判はどうか。こうした信頼性のチェックで少しでも疑念が生じれば、その記事が出版されることはありません。
最終決定:なぜ「両方」のチェックが必要なのか?
最終的に、あなたのブログ記事がGoogleに高く評価される(=検索上位に表示される)ためには、この「編集者」と「校閲者」の両方を納得させる必要があります。どちらか一方だけでは不十分なのです。
- 編集者はOK、でも校閲者がNGの場合 「すごく面白い体験談だけど、情報が古くて間違っている。これでは読者を混乱させてしまう…」 → 評価されない
- 校閲者はOK、でも編集者がNGの場合 「情報は100%正確で、作者も大学教授で信頼できる。でも、専門的すぎて誰も読んでくれないだろう…」 → 評価されない
- 編集者も、校閲者もOKの場合 「信頼できる専門家が、自身の体験に基づいて、読者のために分かりやすく面白い記事を書いている。素晴らしい!」 → 高く評価される!
このように、「読者にとっての価値(HCS)」と「情報の信頼性(E-E-A-T)」、この両輪が揃って初めて、あなたのブログはGoogleと読者の両方から愛される存在となるのです。
アップデート後の世界:勝者と敗者を分けたもの
これまでの解説で、Googleが目指す「理想のコンテンツ」の姿が明らかになりました。では、その理想を現実の検索結果に反映させた今回のアップデートによって、実際にどのようなコンテンツが評価され、どのようなコンテンツが淘汰されたのでしょうか。このセクションでは、アップデート後の「勝者」と「敗者」のコンテンツを具体的に比較し、その明暗を分けた決定的な要因を探ります。この結果を直視することで、私たちがこれから目指すべきコンテンツの姿が、より一層明確になるはずです。
上の図が示すように、評価を上げたのは、まさにHCSとE-E-A-Tを体現したコンテンツでした。特に「実体験に基づくレビュー」や「特定の分野に特化したニッチなブログ」は、その独自性と信頼性が高く評価され、大きく順位を伸ばしました。また、Redditのようなユーザーコミュニティでのリアルな議論や評判(UGC – User Generated Content)も、重要な評価軸として機能し始めていることが分かります。一方で、順位を大きく下げたのは、これまでSEOの常套手段とされてきたようなコンテンツです。公式サイトの情報をまとめただけの「従来型アフィリエイト記事」や、AIを使って大量生産された中身のない記事、さらには中古ドメインの評価を利用しただけのサイトなどは、「読者のための価値がない」「信頼性に欠ける」と判断され、厳しい評価を受けました。
ウェブ上の反応から見るアップデートの真意
実際に、X(旧Twitter)などのSNS上での反応を分析してみると、この傾向はより鮮明になります。ある調査では、今回のアップデートに対する反応として、以下の5つの点が挙げられています。
| 項目 | 評価(感触) | 詳細 |
| 検索精度の向上 | ★★★★☆ | 関連性の高い、質の良い記事にたどり着きやすくなったという肯定的な声。 |
| 個人ブログの回復 | ★★★★★ | 2023年のアップデートで落ち込んでいた良質な個人ブログがV字回復し、喜びの声が多数。 |
| 技術への賞賛 | ★★★☆☆ | スパム検知の精度など、Googleの技術的な進歩に一部の専門家から驚きの声。 |
| 順位変動への戸惑い | ★★☆☆☆ | 評価を下げた一部の運営者からは、理由が分からず戸惑う声も。 |
| コンテンツ作成への影響 | ★★★★☆ | 多くの運営者が「質の高いコンテンツを作らなければ」という意識を強く持つようになった。 |
この反応からも分かる通り、今回のアップデートは、誠実にコンテンツを作成している個人ブロガーや小規模なメディア運営者にとっては、大きなチャンスとなりました。一方で、テクニックに頼っていた運営者にとっては、厳しい現実を突きつけられる結果となったのです。これは、Googleが「誰が、誰のために、何を書いているのか」という、コンテンツの根源的な価値を、これまで以上に重視するようになったことの何よりの証拠と言えるでしょう。
初心者のためのサバイバルガイド:明日からできる3つのこと
ここまで、Googleの理念から最新技術、そしてアップデートがもたらした影響まで、非常に多くの情報を見てきました。「頭では分かったけど、じゃあ具体的に何をすればいいの?」と感じている方も多いと思います。ご安心ください。この最後のセクションでは、難しい話は一切抜きにして、ブログ初心者の方が「明日からすぐに実践できること」を、3つのシンプルなアクションプランにまとめました。小手先のテクニックではありません。これからの時代で、読者とGoogleの両方から長く愛されるブログを育てるための、本質的なアプローチです。この3つを心掛けるだけで、あなたのブログは必ず良い方向に進み始めます。
1. コンテンツ戦略:「好き」と「体験」を正直に書く
まず何よりも大切なのは、あなたの「大好き」という情熱と、あなた自身の「体験」を、正直な言葉で綴ることです。お金儲けのためだけに、興味のないジャンルの記事を無理に書くのはやめましょう。情熱のない文章は、読者にもGoogleにも見抜かれてしまいます。それよりも、あなたが寝食を忘れるほど夢中になれること、誰に頼まれなくても語りたくなるようなことをテーマに選びましょう。そして、そのテーマについて、あなた自身が体験したこと、感じたことを、自分の言葉で書いてください。成功談だけでなく、失敗談もまた、読者にとっては非常に価値のある「一次情報」です。あなたらしさが、最高のオリジナリティになります。
2. 信頼性の構築:「私はここにいます」と顔を見せる
次に、読者に対して誠実であり、「誰が」書いているのかをオープンにすることです。インターネットは顔が見えない世界だからこそ、発信者の「人柄」や「信頼性」が重要になります。完璧な人間である必要はありません。簡単なもので良いので、あなたのプロフィールページを作り、どんな人物がこのブログを書いているのかを伝えましょう。SNSアカウントがあれば、連携させて日々の活動を見せるのも良い方法です。また、記事内で何かを断言する際には、その根拠となる情報源(公式サイトや公的機関のデータなど)へのリンクをきちんと示すように心掛けましょう。こうした一つひとつの誠実な姿勢が、読者とGoogleからの「信頼」を育んでいきます。
- 参考リンクの例 Googleが公開している「質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス」は、どのようなコンテンツが評価されるかを理解する上で非常に役立ちます。ぜひ一度、目を通してみてください。 Google 検索セントラル – 質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス
3. ブログの整備:読者をおもてなしする環境を作る
最後に、読者がストレスなく快適に記事を読める環境を整えることも忘れてはいけません。どんなに素晴らしい内容の記事でも、表示が遅かったり、広告が邪魔で読みにくかったりすれば、読者はすぐにページを閉じてしまいます。特にスマートフォンからのアクセスが主流の現代では、モバイル画面での読みやすさは必須条件です。文字の大きさは適切か、行間は詰まりすぎていないか、画像を多用してページの表示が重くなっていないか。自分のブログを読者の視点で見返し、改善できる点がないかを探してみましょう。読者を大切におもてなしする気持ちが、Googleからの評価にも繋がります。
今回のGoogleアップデートは、多くのブロガーにとって、自身のブログ運営のあり方を根本から見つめ直す大きなきっかけとなりました。小手先のSEOテクニックが通用しなくなり、コンテンツの「質」と「信頼性」が何よりも重視される時代が本格的に到来したのです。しかし、これは決して悲観すべきことではありません。むしろ、本当に価値のある情報を誠実に発信している人にとっては、正当に評価されるチャンスが巡ってきたと言えるでしょう。難しい言葉に惑わされず、ただひたすらに「読者のために」という原点に立ち返ること。情熱と誠実さこそが、この新しい時代を生き抜くための、最も強力な武器になるはずです。



コメント