スマートホーム化を進める中で、多くの方が一度は導入を検討する「スマートロック」。しかし、ぼくはこれまで「鍵の最終判断は人間がすべきだ」という考えから、導入を見送ってきました。便利な反面、万が一のバグや誤作動で意図せず玄関が開いてしまうリスクを考えると、どうしても踏み切れなかったのです。しかし、子どもの成長と共に生活スタイルが変化し、ついに我が家もスマートロックを導入する日が来ました。ただし、それは一般的な使い方とは少し違う、「片側だけスマートロック」という、安全性と利便性を両立させるための、ぼくなりの最適解です。ここでは、その結論に至った経緯と、導入にあたり徹底比較した「SwitchBot ロック Pro」と「SwitchBot ロック(無印)」の違いについて、詳しくお話しします。
我が家の玄関セキュリティ、基本方針は「人間が主役」
我が家のスマートホーム化は、照明やエアコン、窓の開閉センサーなど、多岐にわたります。しかし、玄関の鍵だけは意図的に手動のままでした。それは、どんなに技術が進歩しても、家族の安全を守る最後の砦は「人の意思」であるべきだと考えていたからです。この章では、その基本方針と、それを支えてきた仕組み、そして今回その方針を一部見直すに至った背景についてお話しします。
スマートロックを導入しなかった、これまでの理由
世の中でスマートロックの利便性が語られるようになって久しいですが、ぼく自身の考えは一貫していました。それは、「機械は意図しない動作をする可能性がある」という、システムに対する根本的な向き合い方です。例えば、ファームウェアのアップデートに潜んでいたバグで、ある日突然、家の鍵がすべて解錠されてしまったら?あるいは、クラウドシステムの障害で、ロックが勝手に開いてしまったら?一度でも起これば取り返しのつかない事態です。だからこそ、ぼくはこう考えていました。
鍵の施錠・解錠という行為は、利便性よりも確実な安全性が優先されるべきだ。そして、その最終的な判断と実行は、必ず人間が担うべきである。

うちのSwitchbotアプリだよ。
まだまだ下に続きます。各部屋に温度計もあるしね。

この思想に基づき、我が家では鍵の遠隔「制御」を完全に排除する方針を貫いてきたのです。あくまでスマートデバイスは人間の判断を補助する道具であり、主役は人間。それが、我が家の玄関における絶対的なルールでした。この考え方は、多くのスマートホーム製品を試してきたからこそたどり着いた、自分なりの一つの答えでもありました。利便性の追求が、本来守るべき安全性を脅かすことがあってはならない。その一線を、ぼくは守りたかったのです。
「閉めたっけ?」不安を解消するTP-Link固定カメラの役割


このコ、C110が玄関を見張ってくれています。頑張りすぎて黄色く変色してきましたね^^;
とはいえ、人間である以上、ミスは起こります。家を出た後、「あれ、玄関の鍵、ちゃんと閉めたっけ?」という、あのイヤな感覚。この不安を解消するために、ぼくはスマートロックとは別のアプローチをとっていました。それが、TP-Link製の固定(首振り機能なし)ネットワークカメラ「Tapo C110」を玄関の内側に設置し、鍵だけを監視するという方法です。
この仕組みのポイントは3つあります。
- 遠隔からは「見るだけ」:スマホからいつでも玄関の鍵(サムターン)の状態を映像で確認できます。しかし、カメラなので鍵の開け閉めはできません。あくまで「施錠されているか」を目視で確認するだけ。これで「閉めたっけ?」不安は100%解消できます。
- プライバシーへの配慮:カメラがハッキングされるリスクを考慮し、あえて首振り機能のない固定カメラを選んでいます。画角は玄関の鍵周辺、半径約1m程度に物理的に固定。万が一乗っ取られても、カメラが室内をキョロキョロと見回すことはありません。
- 安定運用のための「スケジュール再起動」:ネットワーク機器は、時として原因不明の不調に陥ることがあります。このカメラを選んだ決め手の一つが、アプリから「毎日決まった時間に自動で再起動する」設定ができることでした。多くのPCが再起動でリフレッシュされるように、カメラ自体を毎日リセットすることで、「いざという時に繋がらない」というリスクを最小限に抑えています。
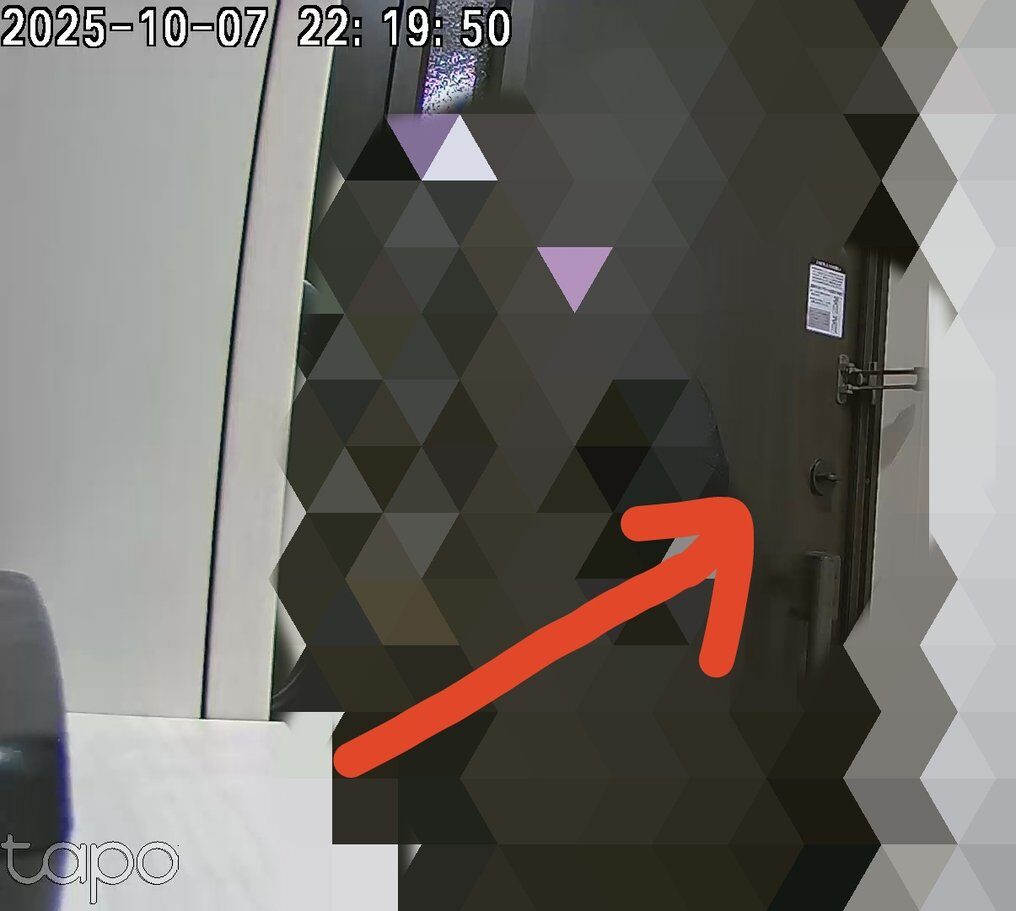

この「人間が施錠し、機械で確認する」という運用で、我が家の玄関の安全性と利便性のバランスは、完璧に保たれていると信じていました。
運用を変えるきっかけ:子どもが最後に出る日の「締め忘れリスク」
完璧だと思っていた我が家のシステムに、転機が訪れます。それは、子どもが成長し、親より後に家を出て、一人で鍵を閉めて登校する日ができたことでした。子どもには、鍵を閉めることの重要性を繰り返し教えています。しかし、子どもは大人ではありません。遊びの約束に気を取られたり、急いでいたりすれば、うっかり鍵を閉め忘れてしまう可能性はゼロではないでしょう。そして、子どもはまだスマートフォンを持っていません。ここで、これまでのシステムの限界が露呈しました。
「遠隔で鍵が開いていることを確認できても、それを閉める手段がない」
カメラで「開けっ放しだ!」と気づいても、家に誰もいなければ、親が慌てて職場から帰るしかありません。これは、あまりにも現実的ではない。これまで築き上げてきた「人間が主役」の思想を守りつつ、この新たなリスクにどう立ち向かうか。大きな課題が、目の前に突きつけられたのです。利便性のためのスマートホームが、逆に大きな不安と不便を生み出しかねない状況。このジレンマを解決するため、ぼくは新しい玄関セキュリティの形を模索し始めました。
「片側スマートロック」という我が家の結論
子どもの「締め忘れリスク」という新たな課題に対し、単純にスマートロックを導入するだけでは、これまでの安全思想が崩れてしまいます。そこで、ぼくがたどり着いたのが「片側だけをスマート化する」というハイブリッドな運用でした。この章では、なぜこの結論に至ったのか、その設計思想と具体的な運用ルールについて掘り下げていきます。
なぜ片側だけ?機械と人間のエラーを吸収する冗長化設計
我が家の玄関ドアには、上下にサムターンが2つ、そしてドアガード(レバータイプのロック)が1つ付いています。この「複数のロック機構がある」という点が、今回の解決策の最大のヒントになりました。ぼくの出した答えは、「サムターン2つのうち、片側だけにスマートロックを設置する」というものです。この設計には、明確な意図があります。それは、機械のエラーと人間のエラー、その両方を吸収できる冗長化です。
- 子どもの締め忘れ(ヒューマンエラー)への対応 子どもが2つとも鍵を閉め忘れて家を出てしまったとします。ぼくは外出先でTapo C110の映像を確認し、「開いている」と気づきます。そして、スマホアプリからスマートロックが設置された片側の鍵だけを遠隔で「施錠」します。これで、最低でも1つの鍵は確実に閉まっている状態を確保できます。防犯上、完璧とは言えなくとも、無施錠状態は回避できます。
- スマートロックの誤作動(マシンエラー)への対応 逆に、万が一スマートロックがバグや故障で勝手に「解錠」してしまったとします。しかし、もう片方の鍵は手動のままです。スマートロックが一つ開いたところで、もう一つの物理的なロックが掛かっていれば、ドアが完全に開いてしまうことはありません。
このように、スマートロックと手動ロックを併用することで、どちらか一方に問題が発生しても、もう一方がバックアップとして機能する。これにより、「無施錠」と「意図しない全解錠」という、最も避けたい2つの最悪の事態を防ぐことができるのです。
遠隔操作は「施錠(LOCK)のみ」に限定する鉄の掟
このハイブリッドシステムを運用する上で、ぼくは自身に一つの絶対的なルールを課しています。それは、「遠隔からの操作は、施錠(LOCK)にしか使わない」というものです。SwitchBotをはじめ、ほとんどのスマートロックアプリでは、遠隔からの解錠(UNLOCK)も可能です。しかし、ぼくはこの機能を意図的に使いません。なぜなら、遠隔解錠を許可した瞬間、「意図しない解錠」のリスクが再び生まれてしまうからです。
- アプリの操作ミスで、ロックするつもりがアンロックしてしまった。
- アカウントが乗っ取られ、悪意のある第三者に解錠されてしまった。
これらのリスクを完全に排除するため、「解錠は、必ず物理キーを持つ人間が、玄関の前で行う」という原則を維持します。遠隔操作は、あくまで「締め忘れ」というヒューマンエラーをカバーするための、施錠方向への一方通行の操作に限定する。これは製品の機能制限ではなく、自らに課した運用上のルールです。この「あえて使わない」という選択こそが、安全性を担保するための重要な掟なのです。利便性を少しだけ犠牲にしてでも、守るべき一線だと考えています。
全てを見守る固定カメラ、変わらぬその重要性
そして、この新しい運用においても、これまで通りTP-Linkの固定カメラ「Tapo C110」の役割は極めて重要です。むしろ、その重要性は増したとさえ言えます。スマートロックを導入すると、アプリ上で「施錠」「解錠」の状態が確認できるため、ついカメラの存在を軽視しがちです。しかし、アプリの表示はあくまでシステム上のステータス。物理的な鍵が本当にその通りに動いているか、それを客観的に証明してくれるのは、カメラの映像以外にありません。
- スマートロックが「施錠完了」と通知してきたが、本当にサムターンは回りきっているか?
- 子どもが手動で片方の鍵を閉めた後、もう片方を閉め忘れていないか?
- ドアガードはしっかり掛かっているか?
これらの最終確認を、人間の目で直接行う。このプロセスがあるからこそ、システムを100%妄信することなく、安心して運用できるのです。「Trust, but verify(信頼せよ、されど確認せよ)」。この言葉通り、スマートロックという便利な仕組みを信頼しつつも、その動作の正しさは必ず自分の目で確認する。そのために、固定カメラは不可欠な存在であり続けます。
SwitchBotロックProと無印、どちらを選ぶべきか徹底比較
「片側スマートロック」という方針が決まったところで、次なる課題は「どの製品を選ぶか」です。我が家ではすでに多くのSwitchBot製品を利用しており、アプリの統一感を考えて、メーカーはSwitchBot一択でした。その中で候補に挙がったのが、フラッグシップモデルの「SwitchBot ロック Pro」と、定番のスタンダードモデル「SwitchBot ロック(無印)」です。この2機種を、我が家の特殊な運用方針に照らし合わせながら、徹底的に比較検討しました。
基本スペックと価格の違いを整理する
まずは、両者の基本的な仕様と価格を表で比較してみましょう。これからスマートロックを選ぶ方にとって、最も気になる部分だと思います。この基本的な違いが、後々の使い勝手や長期的な満足度に大きく影響してきます。単純な価格差だけでなく、素材感やサイズ、そして何より電源方式の違いに注目すると、それぞれの製品が持つキャラクターが見えてきます。
| 項目 | SwitchBot ロック Pro | SwitchBot ロック(無印) |
| サイズ | 約120 × 59 × 83.9 mm | 約111.6 × 59 × 73.2 mm |
| 重量 | 約450g(電池含む) | 約253g(電池含む) |
| 外装素材 | マグネシウム・アルミ合金+PC/ABS | PC/ABS |
| 電源方式 | 単3形アルカリ乾電池×4本 または 専用充電池セット(別売) | CR12Aリチウム電池×2本 |
| 電池寿命 | 約270日(単3電池) / 最長360日(充電池) | 約180日 |
| サムターン互換 | 可変サムターンホルダー(幅0〜23mmに対応) | 固定サイズのアダプター3種 |
| 本体での操作 | クイックキー(ボタン押下で施錠/解錠) | サムターン手動操作のみ |
| 参考価格(税込) | 17,980円前後 | 11,980円前後 |
この表を見るだけでも、Proモデルが多くの点で高機能であることがわかります。特に、電源方式とサムターンへの対応力は、大きな違いと言えるでしょう。一方で、価格は約6,000円の差があり、無印モデルのコストパフォーマンスの高さも魅力的です。
Proと無印、運用の決め手となる電源と保守性
スマートロックを運用する上で、地味ながら最も重要なのが電源です。電池が切れてしまえば、ただの少し重い箱になってしまいますからね。ここでは、両者の電源方式の違いが、実際の運用にどう影響するかを考えてみましょう。
無印モデルが採用しているのは「CR123A」という特殊なリチウム電池です。カメラなどで使われる電池ですが、コンビニなどでは手に入りにくく、価格も比較的高価です。電池寿命は約180日(半年)とされています。コストと入手のしやすさの点で、少し計画性が必要になるかもしれません。
一方、Proモデルは「単3形アルカリ乾電池」4本で動作します。これは、どこでも安価に手に入る最も一般的な電池であり、運用の手軽さは大きなメリットです。さらに、別売の「ロックPro専用 充電式バッテリー」を選べば、USB Type-Cで繰り返し充電でき、ランニングコストを抑えることができます。
どちらを選ぶかは、まさにトレードオフです。初期費用を抑え、コンパクトさを重視するなら無印モデルは非常に魅力的。長期的なランニングコストや電池交換の手間を少しでも減らしたい、というニーズにはProモデルが応えてくれます。
取り付けの互換性と手軽さ:可変ホルダーを持つProの選択肢
後付けスマートロックの設置で、最初の関門となるのが「自宅のサムターンに取り付けられるか」という問題です。サムターンの形状や大きさは、ドアによって千差万別です。
無印モデルは、3種類の大きさの固定サイズアダプターが付属しており、その中から自宅のサムターンに合うものを選んで取り付けます。多くの場合これで対応できますが、もし合わない場合は、サポートに連絡して3Dプリンターで作成した特殊なパーツを送ってもらうなどの対応が必要になることがあります。

Amazonで売ってた3Dプリンターです。さくらチェッカーでみてもレビューが4を超えてました!
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター、組立簡単、500mm/s 高速高精度、全自動キャリブレーション&流量補正、静音造形(<48dB)FDM 3D プリンター、初心者向け、家庭用、日本語UI対応、造形サイズ:180 * 180 * 180mm³
それに対して、Proモデルは「可変サムターンホルダー」という画期的な機構を採用しています。これは、ホルダーの幅をダイヤルで調整することで、0mmから23mmまでの様々な厚みのサムターンに、まるでオーダーメイドのようにピッタリとフィットさせることができます。
これにより、適合しないというリスクが大幅に低減され、誰でも簡単かつ確実に取り付けられるようになっています。特に賃貸住宅などで、原状回復を気にされる方や、取り付けに不安がある方にとっては、この確実性はProモデルを選ぶ大きな理由の一つになるかもしれません。
実際の運用で気になる細かなポイント
スペック比較だけでは見えてこない、実際にスマートロックを日々使っていく上での細かな疑問や注意点があります。手動での操作は大丈夫なのか、遠隔操作の必須条件は何か、便利なオートロック機能の使い勝手はどうか。この章では、そうした実践的な側面に焦点を当てていきます。
手動での開け閉めは問題ない?公式見解と注意点
ぼくが最初に抱いた疑問の一つが、「スマートロックを付けた状態で、これまで通り手でサムターンを回したり、物理キーで開け閉めしたりしても大丈夫なのか?」ということでした。モーターに負荷が掛かって壊れたりしないか、心配になりますよね。これについては、全く問題ありません。 SwitchBotの公式サイトやサポートページでも、「電池が切れた場合は、元の鍵で解錠できます」と明記されています。SwitchBotロックは、あくまでサムターンを外部からモーターで回しているだけの装置。そのため、人間が手で回そうが、鍵穴からキーで回そうが、ロック本体の機構にダメージを与えることはありません。ただし、注意点として、取り付け時に本体とサムターンの軸がズレていると、手動で回した時に妙な引っ掛かりを感じることがあります。これはモーターにも余計な負荷をかける原因になるため、設置の際は慎重に位置合わせを行うことが重要です。スムーズに手動操作できる状態が、正しく設置できている証拠とも言えます。
遠隔操作に必須のSwitchBotハブ、そしてMatter対応の未来
今回の「片側スマートロック」運用の肝となるのが、外出先からの遠隔施錠です。この機能を実現するためには、SwitchBotロック本体に加えて、「SwitchBot ハブ」シリーズ(ハブミニやハブ2など)が必須となります。SwitchBotロック本体とスマートフォンは、Bluetoothで直接通信します。しかし、Bluetoothが届くのは家の中だけ。そこで、ハブが中継器の役割を果たします。
【遠隔操作の仕組み】 スマホ → (インターネット) → 自宅のWi-Fiルーター → SwitchBotハブ → (Bluetooth) → SwitchBotロック
このように、ハブがインターネットとBluetoothの橋渡しをすることで、世界中どこからでも鍵の操作が可能になるのです。我が家のようにすでにSwitchBot製品を多数使っている場合は、既存のハブに接続するだけですぐに利用できます。
オートロック機能とProだけの「一時停止」モード
SwitchBotロックには、ドアが閉まったことを検知して、設定した時間(5秒〜60分)が経過すると自動で鍵を閉めてくれる「オートロック」機能が搭載されています。これにより、鍵の閉め忘れを物理的に防止でき、非常に安心感が高い機能です。しかし、このオートロック、便利な一方で少し困る場面もあります。例えば、ゴミ出しや回覧板を隣に届けるなど、すぐに家に戻ってくる短い外出の際にも、いちいち施錠されてしまうのです。この小さなストレスを解消してくれるのが、Proモデルにのみ搭載されている「自動施錠を一時停止」モードです。本体のクイックキー(ダイヤルボタン)を約2秒間長押しすると、その1回だけオートロックがキャンセルされます。そして、次に手動やアプリで施錠すると、自動的にオートロック機能が復帰するのです。無印モデルの場合、オートロックを切りたい時は、その都度アプリを開いて設定をオフにする必要があります。この一手間の差は、日々の暮らしの中で想像以上に大きな違いとなって現れます。
我が家の最終決定と、この運用で得られる安心感
これまでの比較検討と、我が家の運用思想を突き合わせた結果、ぼくたちの選択の方向性は見えてきました。安全性と利便性、そして長期的な運用コスト。すべてを天秤にかけた上で、このハイブリッドシステムがもたらす究極の安心感について、最後にまとめたいと思います。
結論:あなたのスタイルに合うのはPro?それとも無印?
Proと無印、どちらが絶対的に優れている、という話ではありません。どちらも「片側スマートロック」という運用を十分に満たしてくれる素晴らしい製品です。重要なのは、あなたのライフスタイルや価値観に、どちらがよりフィットするかです。
- SwitchBot ロック(無印)がおすすめな人
- とにかく初期費用を抑えたい
- 本体はできるだけコンパクトで軽い方がいい
- 電池交換の手間やコストはそれほど気にならない
- シンプルな機能で十分
- SwitchBot ロック Proがおすすめな人
- 長期的なランニングコスト(電池代)や入手のしやすさを重視する
- 自宅のサムターン形状が特殊で、取り付けに不安がある
- オートロックの一時停止など、日々の細かな使い勝手を向上させたい
- Matter対応など、将来的な拡張性にも期待したい
ぼく自身の話をすると、長期的な運用の手軽さと、家族が毎日使う上での細かな使い勝手を重視し、最終的にProモデルに心を決めました。しかし、これはあくまで我が家の場合。コストを重視して無印モデルを選び、浮いた予算でキーパッドを追加する、というのも非常に賢い選択だと思います。
SwitchBot以外の選択肢は検討した?
記事を執筆するにあたり、「CANDY HOUSE (SESAME)」や「Qrio」など、他のメーカーのスマートロックについても改めて調査しました。それぞれに素晴らしい特徴があり、魅力的な製品であることは間違いありません。しかし、ぼくの結論として、「すでにSwitchBotエコシステムを構築しているなら、あえて他社製品を選ぶ積極的な理由はない」というものでした。
- アプリが分散する:鍵の操作だけ別のアプリ、というのは非常に煩わしい。
- 連携が複雑になる:SwitchBotの開閉センサーと連携させる、といったことが難しくなる可能性がある。
- 今回の運用方針を満たせない明確な理由がない:「片側スマートロック」「遠隔施錠のみ」という運用は、どのメーカーの製品でも実現可能です。
もちろん、自宅のサムターン形状がどうしてもSwitchBot製品と合わない、といった物理的な制約がある場合は別です。しかし、そうでなければ、使い慣れたアプリでシームレスに管理できるメリットを優先するのが、最も合理的でシンプルな選択だと、ぼくは考えています。
このハイブリッドシステムがもたらす究極の精神的安全性
こうして、我が家の玄関には、「手動のサムターン」と「スマートロック」、そしてそれらを見守る「TP-Link 固定カメラ」という、三位一体の新しいセキュリティシステムが完成しました。このシステムがもたらしてくれたのは、単なる利便性ではありません。それは、「何が起きても、最悪の事態にはならない」という、究極の精神的な安全性です。
- 子どもが鍵を閉め忘れても、遠隔で施錠できる。
- スマートロックが故障しても、手動の鍵が家を守ってくれる。
- 遠隔操作でミスをしても、施錠しかできないルールだから安全。
- 本当に鍵が閉まっているか、いつでも自分の目で確認できる。
機械を過信せず、かといって否定もしない。人間の最終判断を尊重しつつ、ヒューマンエラーはテクノロジーで賢く補う。もし、スマートロックの導入に、ぼくと同じような不安を感じて一歩を踏み出せずにいる方がいるなら、この「片側だけスマートロック」という選択肢が、その悩みを解決する一つのヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。




コメント