ぼくはこれまで、コジマ×ビックカメラ新座店のミニ四駆コーナーの在庫状況を、期待と不安を抱きながら見つめてきました。最初は「パーツの壁」に心から感動し、次に急速な在庫減少に「コーナー閉鎖」の恐怖を覚え、そして一見すると在庫が復活したかのような棚に戸惑いました。しかし、これまでのぼくの視点は、根本的に間違っていたのかもしれません。問題は、フックが空いているかどうかでも、品揃えの種類でもありませんでした。自分の観察眼の甘さを痛感し、一度立ち止まって考えたことで、ようやくこの棚が発する本当のメッセージに気づけたのです。キーワードは「在庫切れ札」。遠目には商品で満たされているように見えるあの棚は、近づいて初めてその正体を現す、巧みな“幻”でした。この記事は、その錯視のからくりと、白い札が静かに増殖していく記録、そしてその先にぼくが見た、切ない現実についての物語です。

見えていなかった「本当の問題」との対峙
これまでの調査記録を読み返すと、目の前にある最も重要な情報を見落とし、的外れな分析を繰り返していました。しかし、その失敗の過程こそが、真実にたどり着くために必要だったのかもしれません。ある気づきをきっかけに、ぼくの棚に対する「見方」は180度変わりました。それは、物事の表面だけをなぞっていた自分との決別であり、このコーナーが抱える、より深く、より構造的な問題と向き合うことの始まりでした。ここからは、ぼくがどのようにしてその新しい視点を手に入れたのか、その思考の変遷からお話しします。
これまでの反省:「空フック」という曖昧な見方との決別
以前のぼくは、棚の問題を「空フックが目立つ」という言葉で表現していました。商品がなく、フックが剥き出しになっている状態。それを、単純な「品切れ」のサインとして捉えていたのです。しかし、この見方では、この棚が持つ本当の異常さには気づけませんでした。「モーターの在庫はあるじゃないか」「問題はそこじゃない」という感覚的な違和感に対し、ぼくは「品揃えの幅と深さが…」などと、それらしい言葉で取り繕うことしかできませんでした。今思えば、完全にピントがずれていたのです。この棚の異常さは、フックが「空いている」ことではなく、むしろ巧みに「埋められている」点にありました。その事実に気づくまで、ぼくは長い時間、思考の迷路を彷徨うことになります。この大きな過ちに気づかせてくれたのは、自分自身の記録と、それを客観的に見つめ直すという作業でした。
新しい視点:棚の景色が「本物」か「絵」かを見極める
思考が行き詰まった時、ぼくは一度すべての情報を整理し直すことにしました。そして、過去の自分のブログ記事と写真を、全く新しい視点で見つめ直したのです。そこでたどり着いたのが、ごくシンプルな「見方」の転換でした。
遠目で満在庫に見えても、それで判断しない。
近づいて、フックに掛かっているものが「商品そのもの」なのか、それとも「在庫切れと書かれた札」なのかを、一つ一つ見極める。
この考え方に至った時、頭の中の霧が晴れるような感覚を覚えました。

まぁ、パッと見で気づくんだけどね^^;
そうだ、問題はこれだったんだ、と。ぼくがこれまで見ていたのは、商品棚ではなく、商品棚の「絵」だったんだ・・・。この店は、商品が尽きたフックに、商品写真が印刷された「在庫切れ」の札が最後に掛けていたのです。この運用が、棚の本当の姿を見えにくくし、ぼくの目を欺いていた。このごく当たり前の「見方」こそが、この棚が持つ異常性を解き明かす、唯一の鍵だったのです。
なぜ「在庫切れ札」は「空フック」より深刻なのか
では、なぜ「在庫切れ札」はただの「空フック」よりも深刻な問題を指し示しているのでしょうか。その意味合いの違いを整理してみます。
| 状態 | 顧客に与える印象 | 店舗側の意思(推測) |
| 空フック | 「たった今売れたのかも」「すぐ補充されるかも」 「そもそも余ってる」 | 偶発的な品切れ。補充の意思はある(かもしれない)。 |
| 在庫切れ札 | 「当店では取り扱いがあるが、今は在庫がない」 「すぐ入荷するからまた来てね」 | 計画的な品切れ状態。「いずれ入荷する」という無言の約束。 |
「在庫切れ札」は、店舗側がその商品の品切れを公式に認め、「いずれ補充しますよ」という意思表示をしている証拠です。しかし、その「約束」が1ヶ月以上も果たされず、むしろ「札」の数が増え続けている。この事実は、単なる補充遅れではありません。結果として“満タンに見える陳列”が継続し、在庫状況の把握を難しくしている。この「錯視」こそが、この棚の最も根深い問題なのです。
時系列で再検証する「在庫切れ札」増殖の全記録
新しい「見方」を手に入れた今、過去の訪問記録を再検証することで、これまで見えていなかった事実が浮かび上がってきます。あの「在庫切れ札」は、いつから、どのようにして棚を侵食していったのか。感動から始まった物語が、静かな恐怖へと変わっていく過程を、客観的な視点で振り返ります。これは、一つの商品棚で起きた、静かなる変化のドキュメンタリーです。
8月30日(初訪問):すべてはここから始まった。「点」として存在した白い影
ぼくがこのコーナーを初めて訪れ、「パーツの壁」に感動した8月30日。その時の記録として撮影したパノラマ写真が、すべての始まりでした。今、改めてその写真を見返すと、確かに写っているのです。中段のFRPプレートや補強パーツが並ぶ帯の中に、ぽつり、ぽつりと、白地に黒い製品シルエットが描かれた「在庫切れ札」が。当時のぼくは、その物量に圧倒されるあまり、この小さな「点」が持つ意味の重さに気づいていませんでした。

この時は立派なコースに感心していたんです。これがミニ四駆ステーションか~って。でも川越のケイ・ホビーもミニ四駆ステーションだったんだよね。そういえば閉店直後はタミヤのページにもケイ・ホビーへのリンクがまだあったなぁ。
ほとんどのフックには現物が掛かっており、棚の景色に占める「札」の割合はごくわずか。しかし、この時点で問題の「芽」はすでに出ており、しかもその位置は、今も「札の壁」と化している改造の“土台系”パーツの帯(安めのFRPやローラー、カーボンステーはいくらかありました)に集中していました。この小さな伏線が、後にこれほど大きな意味を持つことになるとは、この時のぼくは想像すらしていませんでした。
9月下旬~10月3日:「点」から「帯」へ。札が面で広がる恐怖
9月に入り、ぼくは棚の在庫が急速に失われていくのを体感し、「コーナー閉鎖」という言葉が頭をよぎり始めます。そして、その不安が確信に変わったのが、10月3日でした。その日、一見すると棚は商品で埋まっているように見えました。しかし、よくよく近づいてみると、その正体は無数の「在庫切れ札」だったのです。8月末には「点」だった白い影は、この1ヶ月で明らかにその数を増やし、互いに繋がり、連続した「帯」を形成していました。特に、マシンの骨格となるFRP/カーボン系のステーや、ブレーキ、補強プレートといった、改造の「土台」となるパーツが並ぶエリアは壊滅的でした。フックの半分以上が「在庫切れ札」で埋め尽くされ、もはや現物を探す方が難しいほどです。これは、もはや偶発的な品切れではありません。特定のカテゴリのパーツの補充が、継続的に機能していない可能性を示唆しています。点在していた問題が、線となり、そして面となって棚を侵食していく。その光景は、静かな恐怖を感じさせるものでした。
10月10日(最新報告):景色の大半が「札」に置き換わった現実
そして、先日10月10日にあらためて撮影した最新の写真。この状況を、新しい「見方」で改めて評価します。



写真の画角から、改造の土台となるFRP/カーボン製ステーが並ぶ、中段の一帯に注目してみました。そこにあるフックの数をざっと数え、どれだけが「現物」で、どれだけが「在庫切れ札」かを見てみると、その現実に愕然とします。FRPステーはほぼ全滅。ベアリングローラーも全滅していました。そう、「在庫切れ札」で占められていたのです。 もはや「品切れが混じっている」というレベルではありません。改造のどだいとなるパーツ棚の大半が、本物の商品から、商品の「絵」が描かれた札へと、置き換わってしまっている。この棚の今の姿が何よりも雄弁に物語っていました。
なぜこの状況が続くのか?考えられる要因の再整理
この「在庫切れ札だらけの棚」という不可解な状況は、一体なぜ生まれるのでしょうか。断定はできませんが、これまでの観察と他店との比較から、いくつかの可能性が考えられます。これは、ぼくが提示する仮説であり、真実そのものではありません。しかし、この謎を解き明かすための一助にはなるはずです。
他店比較で明確になった「コジマ新座店固有の問題」
この問題を考える上で、決定的なヒントとなったのが、近隣の競合店である「ヤマダデンキ狭山店」との比較です。
| 店舗名 | 観察条件 | 在庫状況(土台系パーツ) | 結論 |
| コジマ×ビックカメラ新座店 | 10月3日、改造“土台系”帯を中心に目視 | ほぼ全て「在庫切れ札」で埋め尽くされている | 極めて異常 |
| ヤマダデンキ狭山店 | 10月4日、同等のカテゴリ帯を中心に目視 | 豊富に在庫あり。一部欠品のみ(点レベル) | 正常 |
この同時期の比較が示す事実は、ただ一つです。問題の原因は、タミヤからの供給不足や、地域全体の物流停滞といった外的要因ではあり得ない、ということ。同じ埼玉県内で、これだけ対照的な在庫状況が生まれている以上、原因はコジマ新座店、あるいはビックカメラグループの内部にあると考えるのが自然です。
本ブログが提示する仮説の再提示
これらの事実を踏まえ、ぼくが考えている仮説を改めて整理します。
- 仮説①:売場の集客効果と仕入れ採算のKPI不一致 ミニ四駆コーナーは、店舗奥へ顧客を誘導する「集客装置」としての役割を期待されている。一方で、商品管理部門は、単価が安くロット単位での仕入れが必要なGUPを「採算性が低い」と判断し、発注を許可しない。この「部門間のKPI(重要業績評価指標)の不一致」が、矛盾した状況を生んでいる可能性。
- 仮説②:システム上の問題 発注、配分、棚割の更新といった、バックヤードのシステムが、このカテゴリにおいて継続的に機能していない可能性。担当者の不在や引き継ぎミス、あるいはシステム自体の不具合など、大企業ならではの組織的な課題が背景にあるのかもしれません。
- 仮説③:「客寄せパンダ」的運用の意図 指摘できるのは、棚が“在庫切れ札”で満たされて見える状態が継続していることです。本ブログの見立てでは、これを意図して「見せ方」を優先し、実需との乖離が生じている可能性も考えています。
いずれの仮説が正しいかは、外部からは判断できません。しかし、何らかの内部的な要因が、この不可解な状況を生み出していることは、ほぼ間違いないでしょう。
それでもぼくがこの場所を見守る理由
ここまで、コジマ新座店のミニ四駆棚が抱える深刻な問題を、客観的な事実と仮説を交えて記録してきました。その内容は、決して明るいものではありません。しかし、それでもなお、ぼくはこの場所を見捨てる気にはなれないのです。なぜなら、そこには矛盾と共存する、確かな魅力と可能性がまだ残されているからです。最後に、このコーナーに対するぼくの切ない思いと、これからのスタンスについてお話しさせてください。
ミニ四駆ステーションという看板の重み
コジマ新座店は、タミヤ公式の「ミニ四駆ステーション」です。それは、単なる売り場ではなく、地域のミニ四駆文化を支え、ファンが集うコミュニティの拠点としての役割を期待された場所である証です。

現状は、その看板に恥じる状態であると言わざるを得ません。指摘できるのは、ステーションらしい“基礎パーツの安定供給”が現状では見えにくいことです。しかし、だからこそ、ぼくはこの看板が完全に降ろされてしまう前に、状況が好転することを願わずにはいられないのです。この場所がステーションでなくなってしまった時、地域のレーサーたちはどこへ行けば良いのでしょうか。その重みを、お店側にもう一度思い出してほしい。そんな切実な思いがあります。
立派な常設コースが語る「矛盾」と「切なさ」
この問題の根深さと切なさを象徴しているのが、立派な常設コースの存在です。広々とした3レーンの立体コースと、十分なピットスペース。そこには、間違いなく「ここでミニ四駆を楽しんでほしい」という、かつての店舗側の熱意が感じられます。しかし、そのすぐ隣には、改造の基礎となるパーツが全く手に入らない「札の壁」がそびえ立っている。
コースは立派。だからこそ切ない。 走らせる土台を作るためのパーツ帯だけが、ずっと『札』で埋まっている。
このあまりにも大きな矛盾。走らせる場所は提供するが、マシンを進化させるための部品は売らない。このちぐはぐな状況が、ぼくの心を締め付けるのです。この素晴らしいコースがあるからこそ、ぼくはこのコーナーの復活を諦めきれない。いつか、このコースで走らせるためのパーツを、隣の棚でワクワクしながら選べる日が戻ってくることを、心から願っています。

静かな期待と、これからの定点観測
ぼくのスタンスは、これまでも、そしてこれからも変わりません。
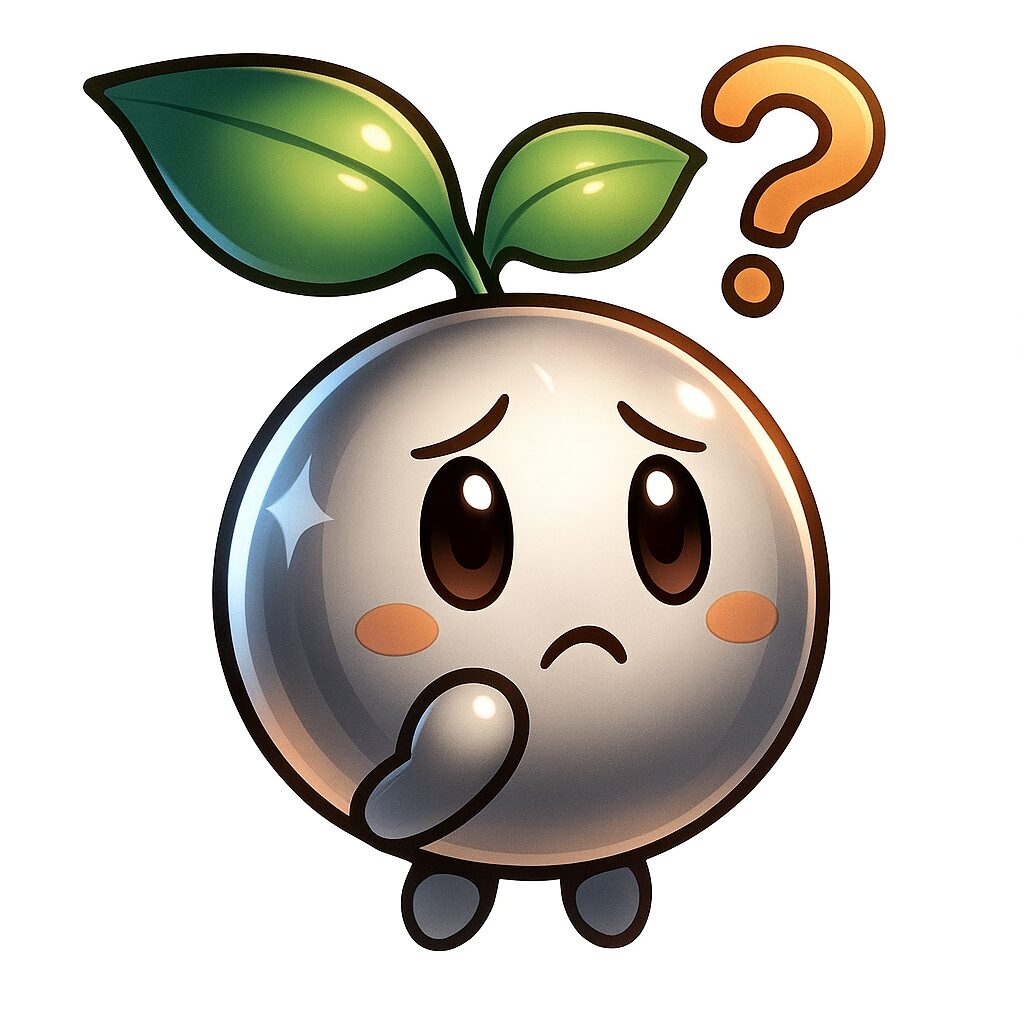
いつ入荷するんですか?
直接問い合わせをしたり、是正を要求したりするつもりはありません。それはぼくの役割ではないと考えています。ぼくができるのは、一人のファンとして、このお店が好きだからこそ、静かに、そして客観的に、この場所の変化を見守り、記録し続けることだけです。
この記事で確立した「棚の景色がどれだけ『札』に置き換わってしまったか」という見方を使い、今後も淡々とログを取っていきます。その景色の変化が、このコーナーの未来を占う、何よりの指標となるはずです。この切ない定点観測の先に、かすかな希望の光が差すことを信じて、これからもこの場所へ通い続けようと思います。





コメント